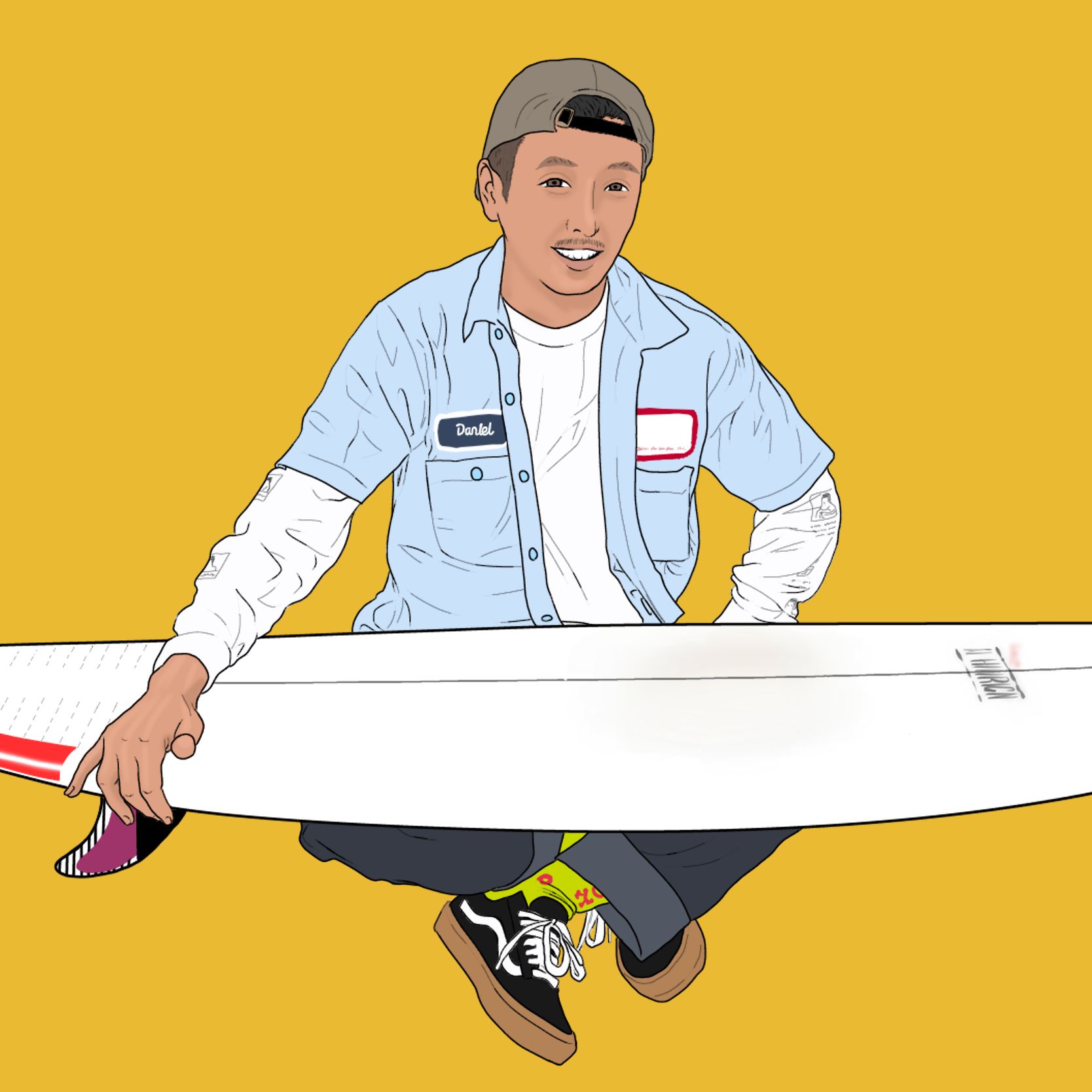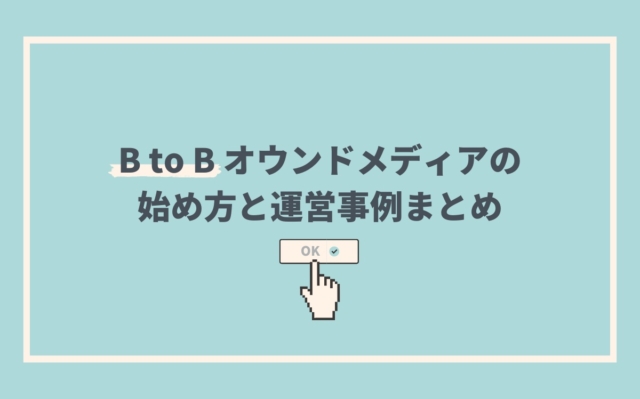これまでオウンドメディアはBtoCビジネスが主流でしたが、BtoBビジネスのオウンドメディアも広がっており、成果につなげている企業が増えてきています。
では、BtoB企業がオウンドメディアを始めるにあたって、具体的にどのようなステップを踏み、運営していけば良いのでしょうか。
本記事では、BtoBビジネスをおこなっている企業が、これからBtoB向けオウンドメディアを立ち上げるための方法から、成果につながる運営方法のコツなどを解説します。
成功している企業の事例も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
BtoB企業にも広がる「オウンドメディア」とは?

オウンドメディア(Owned Media)とは、『自社が保有するメディア』を意味し、ホームページ/ブログ/Webマガジンなどが該当します。
オウンドメディアを運営することで、ユーザーの関心を高めて自社製品の購入やサービスの売り上げを拡大させていくことが狙いです。
BtoB(Business to Business)とは、企業間でおこなわれるサービス/ビジネスを指し、オウンドメディアとBtoBを掛け合わせた『BtoBオウンドメディア』は、企業が企業に対して自社の製品/サービスに関する情報発信やマーケティングをおこなうメディアを意味します。
企業向けのBtoBオウンドメディアを持つことで、同じ製品を販売している競合他社との差別化を図れたり、見込み顧客に対してよりわかりやすく案内ができたりするため、ニーズに合った情報を提供することができます。
BtoB企業が『オウンドメディア』を運営するべき理由
BtoBマーケティングにはWeb広告やSNS運用などさまざまな手段がありますが、その中でもオウンドメディアを運営するべき理由として、顧客と自社の商品やサービスとの接触機会を増やせることが挙げられます。
オウンドメディアでは、継続して顧客が抱える悩みや課題の解決につながるコンテンツを発信していきます。このコンテンツに対して価値を感じ、何度もサイトを訪れてもらえるようになれば、自社の商品やサービスの接触機会も増やせることにつながります。
また、各検索キーワードに適したコンテンツを作成することで、検索エンジンの上位に表示されやすくなり、潜在顧客からのアクセスにつなげることができます。
BtoB企業が『オウンドメディア』を運営する目的
オウンドメディアを運営する上で、最終的な目的は成約数の増加になることがほとんどですが、それ以外の目的を設定することもあります。例えば、以下のような目的です。
・認知拡大
・ブランディング
・顧客満足度の向上
自社商品やサービスの知名度が低くい場合でも、オウンドメディアで有益な情報を発信していくことで認知してもらえる機会を増やすことができます。
専門的な情報をオウンドメディアを通して発信することができれば、ターゲット層に対して業界における専門知識やノウハウをメディアを通して伝えることが可能です。
商品やサービスに関するノウハウだけでなく、活用事例/FAQなどを発信することで、商品やサービスの価値が高められ、顧客満足度の向上が期待できます。
BtoB企業がオウンドメディアを運営するメリット

BtoBオウンドメディアを運営することで得られるメリットは主に以下が挙げられます。
・まだ競合が少なく差別化しやすい
・ターゲットを絞って発信できる
・営業ツールとして活動できる資産になる
・商品やサービスを詳しく公開できる
・上位表示で安定的なリード(見込み客情報)獲得が見込める
・長期的なブランディングにつながる
詳しく解説していきます。
まだ競合が少なく差別化しやすい
BtoBオウンドメディアは、まだ取り掛かっている企業が少ないのが現状です。BtoB企業がオウンドメディアを持っているだけでも、優位性があり、他社との差別化も図れます。
また、BtoBビジネスはニッチな領域の製品/サービスを扱っている場合が多いため、オウンドメディアも独自性のあるコンテンツになる傾向があります。
専門性の高い商品にオウンドメディアにおけるマーケティングで、さらに自社製品の強みや魅力を訴求することが可能です。BtoB企業はBtoC企業に比べてWebマーケティングの対策ができていない傾向にあるので、しっかりWeb戦略をおこなえばインターネットでの検索上位が狙いやすいといえます。
ターゲットを絞って発信できる
BtoBオウンドメディアで大切なのは、ターゲットを絞って情報発信ができることです。そのため、適切に自社製品/サービスをアピールできます。
ターゲット戦略を事前におこなうことが成果につなげる肝となり、ターゲットユーザーの人物像を明確にして、需要にあったコンテンツを発信しましょう。
BtoBオウンドメディアで発信する情報は、企業が抱えている課題やニーズがメインとなりますが、ターゲットは企業の中の人までイメージすることが大切です。どんな企業や担当者が、何のキーワードで検索するか、抱えている疑問や悩みに対してどのような解決法が提案できるのか、戦略を立てることがポイントです。
ターゲットとなる企業を絞って(エッジを効かせる)コンテンツを発信していく方が、ニーズに刺さり売り上げにつながりやすくなります。普段取引先から質問されることを記事でまとめるのも有効なコンテンツといえます。
営業ツールとして活動できる資産になる
従来の営業活動において、企業側に直接渡していた資料をそのままWebに公開することで、オウンドメディアが営業ツールへと変化しています。
直接企業に営業するのではなく、ターゲット企業が自ら自社を見つけてアクセスしてきてもらえるため、角度の高い見込み客になりやすい傾向があります。
Web上の情報は全世界から365日アクセス可能なので、場所や時間にとらわれず、多くの企業に自社を知ってもらう機会が作れ、自社の個性や商品/サービスの魅力を発信できるメディアです。
商品やサービスを詳しく公開できる
BtoB企業が扱っている商品/サービスは専門性が高く、ニッチなものである傾向があるため、ただ商品情報を紹介しても簡単に理解してもらうことは難しい場合があります。
その点オウンドメディアでは、ユーザーの理解度に合わせて記事を制作したり、情報を網羅して届けたりすることが可能です。
自社や自社製品について知られていなくても、商品に関連するキーワードから自社のオウンドメディアを見つけてもらえたらなら、そのユーザーは潜在顧客といえます。
潜在顧客に対して丁寧に情報を伝えていくことで、見込み顧客を育てること(リードナーチャリング)になり、将来的に顧客獲得へとつなげていけるでしょう。
BtoCと違ってBtoBの場合、企業は一般的に製品の購入やサービスの導入については、検討期間を長くとり慎重になります。
購入前に入念に調べ、自社の商品/サービスに対する理解を深めてもらった後にアクションをとってもらえるため、成約の角度も高くなってくるといえます。
オウンドメディアはいろいろな情報発信が可能です。自社の強みや商品/サービスの魅力を最大にアピールする場としてぜひ活用してみてください。
上位表示で安定的なリード獲得が見込める
BtoBビジネスでは、BtoCほどコンテンツマーケティングの普及が進んでいません。
そのため、まだまだBtoBオウンドメディアの数が少なく、ライバルが少ないのがメリットです。
したがって、
・検索での上位表示が狙いやすい
・検索の上位表示で企業の信用度や好感度が向上する
・検索の上位表示で企業のブランディングが期待できる
といった大きなアドバンテージを得ることができます。
一方で、BtoBオウンドメディアが育って、実際に受注を得るなどの効果が出るまでには、時間がかかり長期戦になってしまうことは拒めません。
しかし、将来的に安定的な顧客獲得につながっていくオウンドメディアに力を注ぐのは、賢い投資です。
競合が少ないうちに、Web戦略としてBtoBオウンドメディアを運営していくことで差別化を図れます。クオリティーの高いコンテンツを根気強く発信し続けていくと、検索エンジンからも評価を得られ、狙ったキーワードで上位表示の実現につながります。
長期的なブランディングにつながる
BtoBオウンドメディアでコンテンツを発信することは、企業のブランディングを行うことができます。
BtoB商品/サービスに関連する専門的でニッチな情報は、なかなかWeb上にも上がっていないので、オウンドメディアを通して役立つ情報や解決策を提供するだけでも、見込み顧客に良い印象を与えることができます。
ただ単にオウンドメディアを保有するだけではアクセス数を伸ばせません。
SEO対策をしたり質の高い記事を書いたりと、Webマーケティングにおいてのスキルは必要ですが、正しいマーケティングをおこなえば、長期的なブランディングへとつながり、安定的に集客を見込めるようになります。
BtoB企業がオウンドメディアを運営するデメリット

BtoBオウンドメディアの運営は、メリットだけじゃなく、当然デメリットもあります。デメリットは主に以下が挙げられます。
- 専門知識が必要
- 結果が出るまで時間がかかる
- 継続にはコストがかかる
デメリットも理解した上で導入を検討することをおすすめします。
専門知識が必要
BtoBオウンドメディアでは、ターゲット企業側からの信頼や好感を得るためにも、信頼性の高い情報発信と、Webマーケティングの知識が必要です。
Webマーケティングとは、SEO対策/Webライティング/SNSなどのスキルが必要となり、これらの理解が深くない状態で取り掛かってしまうと、オウンドメディアとして十分な成果を上げることが難しくなります。
もし自社にWeb専門のスタッフを配置できないのであれば、Webマーケティング専門のコンサルティング会社やスキルの高い人材に外注するのもひとつです。
結果が出るまで時間がかかる
オウンドメディアは検索エンジンに評価され、狙ったキーワードで上位表示されるまでに時間がかかります。質の高い記事が定期的にアップされることや、いろいろなメディアからリンク/アクセスされることで徐々に信用を得て成長し、評価を高められます。
オウンドメディアをリリースしたからといって、すぐに受注が入ったり、効果が得られたりするものではないため注意が必要です。
長期スパンで戦略を立て、コツコツと励んで効果を狙っていく忍耐力が求められます。最初は労力と得られる結果が割に合わないと感じる方も多いですが、適切な運用を行うことで数値に変化が出てきます。
半年から1年は、辛抱強く運営していくことを覚悟して取り組むことを念頭に置かなければいけません。
継続にはコストがかかる
オウンドメディアの運営で大切なことは継続です。クオリティーの高い記事を定期的に公開していく必要があります。
オウンドメディアの成功には、初期の設計と長期的にコンテンツを配信し続ける仕組みづくりが重要です。中途半端なオウンドメディアの運用では、結果が出ずに時間だけが過ぎてしまう可能性もあります。
成果を上げていくために、他社に外注する予算やスタッフの採用を検討していく必要があるでしょう。
BtoB企業のオウンドメディアの始め方

企業がBtoBオウンドメディアを始める際の大まかなステップは以下です。
- 運営目的とKPIを定める
- ターゲットとテーマを策定する
- カスタマージャーニーマップを作成する
- CMSを導入しコンテンツをストックしていく
それぞれ詳しく解説します。
運営目的とKPIを定める
オウンドメディアを立ち上げる際は、まずその運営目的とKPI(ゴール)を明確に設定します。曖昧な目的やゴール設定ではなく、具体的に数値に現すことが大切なポイントです。
オウンドメディアを通して、具体的にどのような結果が欲しいのか、目標設定を数字化することが、成功への一歩です。
例)
運営目的
・自社のブランディング強化
・見込み客の商品に対する意欲/関心の増加
KPI設定
・1ヶ月あたりの目標PV数/閲覧者数/問い合わせ件数/購入者数
・セッション数から問い合わせ数の割合が○%アップ
達成したいゴールによって、運営手法や記事の内容、発信方法も変わってきます。
ゴール設定から逆算して、オウンドメディアの運用方法を考慮すると、方向性も定まりやすくなります。自社の方針やオウンドメディアの軸を定めて、一貫性のあるメディアにすることを目指してください。
ターゲットとテーマを策定する
BtoBオウンドメディアでは、ターゲットとテーマを絞って、コンテンツを制作することが重要です。
オウンドメディアに訪れるユーザーのニーズはそれぞれ異なります。ニーズに合った情報を提供するためにも、ユーザーが求めている情報を的確に把握し、ポイントで紹介することで、ユーザーの要望に沿ったコンテンツを発信することができます。
ユーザーの興味や関心を高めることで、商品/サービスの問い合わせや申し込み期待できるようになります。
押さえておきたい「コンテンツマーケティング」とは?
コンテンツマーケティングは、コンテンツを用いたマーケティングを指し、ターゲットユーザーが最も価値を感じる内容や情報を発信してコミュニケーションを図ります。
その中でも、ターゲットを狙って情報を発信する戦略が、成果を生み出す秘訣といっても過言ではありません。
アメリカでは、とくにコンテンツマーケティングが盛んで、その理由はBtoB企業のユーザー側の年齢層が若くなってきていることが影響しています。
インターネットを活用した情報収集で購入を決める企業が増えており、日本でも同様にコンテンツマーケティングが取り入れられ始めました。ターゲット企業の抱えている悩みや課題を認識し、どんな提案ができるのか、テーマを絞ってコンテンツを発信することを心掛けなければいけません。
カスタマージャーニーマップを作成する
『カスタマージャーニーマップ(Customer Journey Map)』は直訳すると『顧客の旅の地図』です。
見込み客(企業)から実際に商品やサービスを購入してもらうまでのプロセスとなる行動や思考、感情の移り変わりをまとめた地図のようなものを指します。
カスタマージャーニーマップでは、以下の点を明確にする必要があります。
・ユーザーの抱えている悩みや課題
・想定する検索キーワード
・記事に対する反応とその後のアクション
・実際に購入する際の検討事項
ターゲットユーザーがコンバージョンするまでの各段階を深く掘り下げていくことで、自社とその商品/サービスの特徴や役割をあらためて深く理解できます。
ターゲットユーザーの立場になって分析することで、効果的な営業方法や販売手段などを見つけやすくなります。
CMSを導入しコンテンツをストックしていく
方向性が決まったら、CMSを導入し、コンテンツを準備していきます。
『CMS(Content Management System)』とは、『コンテンツ管理システム』のことで、オウンドメディアなどのWebサイトに使われるシステムを意味します。
Webサイトに必要なプログラムやテキスト/画像/テンプレートといった情報を保存し管理するシステムで、オウンドメディアの運営をスムーズに手助けしてくれるものです。
CMSを導入するまでは専門的な知識が必要ですが、導入後の運用フェーズにおいては、Webの知識がなくてもワードを書く感覚で記事の公開ができるようになります。
CMSの導入は専門業者に依頼し、商品やサービスの紹介となる記事制作は自社で制作するか、記事のみを業者に依頼する形が一般的といえます。
BtoB企業がオウンドメディアを運営する際に起こり得る失敗例

BtoB企業の中には、オウンドメディアを運営しているにもかかわらず、目的を達成できず悩む企業も少なくありません。
なぜオウンドメディアを運営しても成果につながらないのでしょうか。ここからは、BtoB企業が陥りやすいオウンドメディア運営の失敗例をご紹介します。
動線設計がうまくいっておらずCVにまでつながらない
SEO対策に力を入れることでPV数を増やせますが、なぜかCVにつながらないケースもあります。CVにつながらない原因として、動線設計がうまくいっていない可能性が考えられます。
記事内にすぐ資料請求や購入ページへ移行できるように、CTA(Call To Action)ボタンが設置されることは多いです。しかし、CTAが適切な場所に設置されていないとユーザーは行動に移せず、CVまで至らない可能性もあります。そのため、オウンドメディアを運営する際には、記事内の導線設計についても考えることが大切です。
オウンドメディアはCVにつながらなかったとしても、長期的な施策として考えると価値の高いコンテンツです。潜在顧客の増加や自社の認知度向上、ブランディングなどが期待できますし、オウンドメディアを見たユーザーが別の経路から問い合わせや成約にいたっている可能性もあります。
オウンドメディアは直接的なCVにつながるとは限らないことも念頭に置きつつ、取り組むことが重要です。
社内のリソース不足でメディアを更新できない
せっかくオウンドメディアを作ったとしても、社内のリソース不足によって更新が難しくなる場合もあります。オウンドメディアを運営するためには記事の作成に加え、既存記事の更新作業なども必要です。
社内にオウンドメディアの運営を担当するチームや社員がいれば良いですが、主業務と兼任しているケースも少なくありません。この場合だと、主業務が忙しくなることでメディアの更新がストップし、失敗に陥ってしまいます。
オウンドメディア運営のすべてを内製で賄おうとすると失敗する恐れがある場合は、サイトの立ち上げから運営まで外注に任せた方が安心です。
もしくは、部分的に外注をして運営をサポートしてもらう方法を検討することができます。
コンテンツの情報が古いまま残ってしまっている
BtoBオウンドメディアは長期的に運営することが前提であり、定期的にコンテンツを更新していく必要があります。記事を制作した時点では最新だった情報が、時間が経過していく中で古くなっていき、場合によっては間違った情報の発信につながる可能性もあります。社会は常に変化し続けているため、コンテンツの情報も新しくアップデートしていかなくてはなりません。
コンテンツの情報が古いまま残っていると、検索エンジンからも評価されず、上位表示されない可能性が高いです。
また、更新されていない記事を閲覧したユーザーから「最新の情報を持っていない」と判断され、企業の信頼度にも悪影響を及ぼしてしまう可能性もあります。
BtoB企業がオウンドメディアを成功させるポイント

BtoB企業がオウンドメディアを賢く運営する上で、押さえておきたい要点は以下が挙げられます。
- 運営目的を明確にする
- セッション数を意識してコンテンツを作成する
- コンスタントに発信し、内容を最新に保つ
- 問い合わせなどの動線をきちんと設計する
- 無理なく運営できる体制をつくる
詳しく解説していきます。
運営目的を明確にする
運営目的は漠然としたものではなく、はっきりと明確化し、具体的な数値にして現すことが成功の秘訣の一歩です。
当たり前のように感じられるかもしれませんが、できていないケースが多々あります。何を目的にするかによって、打ち出す施策が変わるため、目的が定まらずにただオウンドメディアを立ち上げて、闇雲に情報を公開しても意味がありません。
運営目的が定まれば、自社の中での意思疎通もスムーズになり、企画やアイディア/改善案などが出しやすくなるといったメリットがあります。
セッション数を意識してコンテンツを作成する
セッション数とは、特定の期間内にWebサイトへ訪問したユーザーの訪問回数のことで、オウンドメディアを分析していく上で必ず見ていく必要がある指標の一つです。
セッション数が多ければ、それに伴いコンバージョン数(資料ダウンロードや問い合わせ数などの目標数値)も上がることを期待できます。
どんなに良いオウンドメディアを作ったとしても、それを見てくれる人、つまりセッション数が少なければ、問い合わせや購入にはつながりません。
例えば、セッション数を増やす施策のひとつに『検索ボリュームが多い記事を作成する』方法があります。
製品と関連する検索数が多いキーワードを使って、記事を書き、アクセスアップを図る手法です。
記事を公開した後、セッション数はどれくらいか、週に1度はチェックしましょう。
オウンドメディアを正しく分析するためにも、アクセス数やセッション数を把握していなければ検証ができません。
できる限り多くのユーザーの目に留まるように、ターゲットユーザーに検索されるキーワードを考え、コンテンツを制作することがポイントです。
ただ単に、商品紹介や宣伝をするのではなく、企業独自のストーリーや背景を商品/サービスと共に紹介することで、ユーザーに印象付けができるでしょう。
コンスタントに発信し、内容を最新に保つ
BtoBオウンドメディアでは、常に最新の情報を顧客に提供することが求められます。
せっかくオウンドメディアを運営していても「記事の更新が継続できていなかったり」「間違った」「古い情報のまま記事を公開している」などを行っている場合、自社の信用を失ってしまいます。
新しい記事を定期的に公開するスケジューリングと、過去記事の情報が古いままではないかチェックする体制を整えて徹底することを怠ってはいけません。
情報は時代と共に変わっていきます。情報が古くなっていたらリライトに取り組み、常に最新の情報を発信するように努めましょう。とくにリライトは、疎かになったり忘れがちになったりするため、記事を書くときに初めからリライトするスケジュールまで組むと忘れることなく取り組みやすくなります。
リライトする際は、記事にどのような情報が不足しているか、改善点を入念にリサーチして「ユーザーのニーズは何か」と仮説を立てながら、執筆することが重要です。
内容をリニューアルする必要がなくても、検索エンジンからのクリック率(CTR)が改善されるようにタイトルや説明文(discription)を工夫することで、流入数を増やすことにつながります。
社内で記事のリソースが確保できないのであれば、ライティングスキルを持ったプロの人材に依頼することをおすすめします。
オウンドメディアの運営を通して、どのようなコンテンツに需要があるのか、反響を分析しながら、記事を更新していくことが成功する秘訣です。
問い合わせなどの動線をきちんと設計する
オウンドメディアのアクセス数が増加しても、そこから問い合わせや商品/サービスの購入につながらなければ、改善する余地があります。
まずは導線を見直しましょう。
ユーザーからのアクション(問い合わせ/資料請求/購入完了)がアクセス数と共に増加しない場合は、資料ダウンロード/問い合わせのボタンやページをチェックします。
・記事のページから誘導したいページへのリンクは設置できているか
・問い合わせしたくなるように働きかけているか
・問い合わせページにエラーが発生していないか
・入力フォームに問題はないか
自社のスタッフは目が慣れてしまって判断がつきにくいケースもあります。
その場合は外部の人に頼んで記事を見てもらうのもポイントです。
中には「一旦問い合わせをすると、もう引き下がれないのではないか」とプレッシャーに感じさせることもあります。その場合の対応策として、資料ダウンロードやメルマガの登録/無料見学会の申し込みなど軽めのアクションをしてもらう方法があります。
顧客を育てるつもりで運用する目線を持つことが大切です。
無理なく運営できる体制をつくる
オウンドメディアを長期的に運営していくためには、無理なく継続できる体制づくりをおこなうことがポイントです。
更新をコンスタントに続けていくためにも、コンテンツ制作の流れをシステム化し、安定したペースで続けていけるように取り組むことが大切になります。
コンテンツ制作チームを組んで「誰がどの役割を担うか」「どのくらいの頻度で更新していくか」など初期段階で明確に決めておくと、記事更新の作業が定着化しやすくなります。
すべて自社で対応するとなると、メディアが大きくなればなるほど負荷がかかるため、ライティングやSEOは外注するなど、外部スタッフをうまく活用することで進行を遅らせずに進めることが可能です。
ある程度コンテンツが蓄積されたら、レビューをする機会も作ってください。
反響がある記事とない記事それぞれ何が良くて何が悪いのかを数値と共に分析し、チームで改善案を出し合うことができます。
オウンドメディアの良いところは、数値が目に見えるため、良い悪いがはっきり把握でき、早急に改善策が打てる点です。メディア運営は、トライアンドエラーで成功に導いていくことが重要になります。
成功しているオウンドメディア事例11選

BtoBオウンドメディアを上手に活用し、売り上げアップに成功している企業の事例を紹介します。
他社のアイデアを参考にしながら、BtoBオウンドメディアのコンテンツ制作に役立てて売り上げ拡大を目指しましょう。
株式会社キーエンス『バーコード講座』
『バーコード講座』は、株式会社キーエンスによる、バーコードの基本原理からJANコードやcode39の構成や使用例、QRコードに代表される2次元コードの仕組みなどについて、わかりやすく解説されているBtoBオウンドメディアです。
ターゲットは解析機器/測定機器などを開発している企業で、専門性が高く高度な知識が求められます。
記事は非常に丁寧に、詳細までしっかりと書かれているため、信頼性も高く、たとえアクセス数が少なくても、必要な人に届けばその後の資料請求や問い合わせにつながりやすいサイトといえるでしょう。
freee株式会社『経営ハッカー』
『経営ハッカー』は、クラウド会計ソフトで知られるfreee株式会社による、経営者/個人事業主に役立つ情報提供の場として運営しているBtoBオウンドメディアです。
テーマは、『会計、経理、人事労務、税務、確定申告、給与計算、起業、会社設立』などで、記事は会計士や税理士などの専門家に外注して執筆されています。
情報量、記事数が多く、ビジネスにまつわるさまざまなトピックに対応しているため、アクセス数も多いことが伺えました。カテゴリーは個人/法人と分けられており、記事の種類も明確なため、ユーザーが迷わず読みたい記事にアクセスできます。
その他にも、サイト内の記事検索から、ユーザーが気になるキーワードで検索できるようになっているので、ユーザーが今まさに求めている情報がすぐに見つかるよう設計されているのが特徴です。
会計について初心者でも、インタビュー記事などを掲載することで取り組みやすさが感じられます。
難しいテーマではありますが、ユーザビリティの高いサイト設計と、初心者に訴求していくコンテンツの配信から、考え抜かれた運営であるといえるでしょう。
会計について初心者でも、インタビュー記事などを掲載することで取り組みやすさが感じられます。
難しいテーマではありますが、ユーザビリティの高いサイト設計と、初心者に訴求していくコンテンツの配信から、考え抜かれた運営であると言えるでしょう。
株式会社LIG『LIGブログ』
『LIGブログ』は、株式会社LIGによる、Webサイト、アプリ開発、メディア運営に関する情報発信をしているオウンドメディアです。
BtoBオウンドメディアの成功例としても有名なサイトでもあり、ユーザーの再訪やファンの定着化がしやすいといった特徴が見られました。
ユーザーに有益な情報を発信するだけではなく、自社独自の魅力や個性を伝えたり、社員の個性をうまく活用して彼らをインフルエンサーにしたりと、企業の個性をアピールするオウンドメディアの活用方法として非常に優れています。
多くのPV数を稼ぐ人気エンタメ記事から、SEOなどの情報系の記事まで幅広く対応しているのも強みです。バラエティに富んでいるので、毎日読んでも飽きないのではないでしょうか。
コクヨ株式会社『コクヨマガジン』
『コクヨマガジン』は、文房具やオフィス器具などの販売事業をしている、コクヨ株式会社が運営するオウンドメディアです。
主にビジネスパーソン/学生に向けて、ワークスタイル全般を発信しています。
記事は『学ぶ』『働く』『暮らす』『子育て』といったライフスタイルに合わせたカテゴライズで、さらにハッシュタグやキーワード検索ができ、内容はユーザーの日常に寄り添った興味を惹きやすいコンテンツでした。
文房具と生活をリンクさせたコンテンツを発信することで、潜在的な見込み顧客に対して自社製品への関心を持ってもらうことが狙いではないでしょうか。
サイボウズ株式会社『サイボウズ式』
『サイボウズ式』は、働き方/業務/組織などのビジネスコンテンツを主に発信をしている、サイボウズ株式会社によるオウンドメディアです。
週に3回程度コンスタントに記事が更新されているため、読者が定着しやすいのが良い点です。
タグや気になるワード検索では、ユーザーが求めている情報を見つけやすいようにしてあり、SNSのシェアボタンの数も、サイト内の上部と下部に、また記事内にも目立つ位置に配置されているため、ユーザーが気軽にシェアしやすいよう工夫が施されていました。
文字の記事だけではなく、動画形式で発信活動をしている点も魅力の一つです。
ライターや従業員の人物写真を掲載して、読者に親近感を持ってもらうようにするのも、自社のファン化を増やす工夫として有効です。
株式会社サイバーエージェント『CyberAgent Way』
『CyberAgent Way』は、株式会社サイバーエージェントによる、技術/デザイン/IR/企業文化の紹介などをしているオウンドメディアです。
オウンドメディアを通して、自社採用の強化を狙っています。従業員をまるで俳優やタレントのようにビジュアル演出をすることで、企業に対する憧れを読者に与えているように伺えました。
フォトギャラリーの活用や、おしゃれなデザインでブランディングへの意識の高さがわかります。
従業員インタビューの記事では、サイバーエージェントで働きたいと思わせるような発信活動をしているので、とくに採用ブランディングを強化したいメディアを作りたい方にとって、良いお手本となるでしょう。
エンタメ要素が強いオウンドメディアなので、主に若年層に興味を持ってもらいたい企業は参考にしてみてはいかがでしょうか。
株式会社リクルートホールディングス『Inside Out』
『コーポレートブログ:Inside Out』は、株式会社リクルートホールディングスによる、コーポレートブログで、企業情報や事業紹介など、社内の取り組みを発信しているオウンドメディアです。
リクルートホールディングスは、世界中のステークホルダーに向けて、自社の事業を発信しています。
『サービス』『リーダーシップ』『サステナビリティ』といったジャンルの記事が発信されていました。
ビジュアルもシンプルで派手すぎず、企業の方針やビジョン/ミッション/バリューズ、会社の歴史など、詳細に記載されているため、企業に対しての安心や信用度を与えたいといった狙いが予測できます。
大企業のフォーマルなオウンドメディアですが、CEOや役員からのメッセージを、実際の人物写真や動画を使って発信しており、親しみが湧きやすい印象が持てました。
企業ブランディングに特化したオウンドメディアを作りたい企業は、参考にしてみてはいかがでしょうか。
artience株式会社(旧:東洋インキ株式会社)『コラム』
東洋インキ株式会社は、2024年1月よりartience株式会社へと社名を変更しています。以前運営していたオウンドメディア『1050+』には現在アクセスできない状態となっていますが、コンテンツについては企業サイトの『コラム』に移行されました。
コンテンツは、持続可能な社会を目指すために環境に良い製品の紹介や色彩学などの情報を発信しています。検索キーワードが近年増加している『SDGs』や『持続可能な社会』といった環境に関するキーワードと、自社製品を組み合わせた記事が目立ちました。
商品/サービス情報そのものに対するニーズが低くても、旬の話題を利用することで、自然と自社製品に興味/関心を持ってもらうよう、うまく戦略を立てていると感じられます。
株式会社ガイアックス『ソーシャルメディアラボ』
『ソーシャルメディアラボ』は、株式会社ガイアックスによる、SNSマーケティングに関するコンテンツを提供しているオウンドメディアです。
BtoB企業向けに、どうやってSNSアカウントを活用していけば良いか、SNSでビジネスを成功させるハックを紹介しています。SNSマーケティングは、企業はもちろん個人のスモールビジネスをしている方にも有効なため、幅広いユーザーにアプローチできるでしょう。
記事のキーワードに加えて『Facebook』『Twitter』『LINE』『Instagram』などプラットフォームに分けてカテゴライズされているため、必要な情報を簡単に探すことができます。
マーケティング支援に関連した事業の方は参考にしてみてはいかがでしょうか。
KDDI株式会社
『KDDIトビラ』は、KDDI株式会社による、5GやDXなど『つなぐチカラの進化』や社会課題/環境課題への取り組み、暮らしや文化の変革をテーマにコンテンツを発信するオウンドメディアです。
カテゴリーはつなぐチカラ(通信関連)、5G、DX、社会、カルチャー、環境、暮らしの7種類に分かれ、特集なども組んでコンテンツを発信しています。記事を通じてKDDIがどのような事業を展開し、社会課題/環境課題の解決に取り組んでいるかが見えてきます。1記事あたりの文章量は少なくても内容が充実しており、誰でも読みやすいのが特徴的です。
また、『動画で見る』からは、YouTubeチャンネルに投稿した動画へ直接アクセスできるようになっています。動画は文章に比べてより多くの情報を伝えられることから、効果的なブランディングが図れているといえるでしょう。
株式会社マネーフォワード『Money Forward Bizpedia』
『Money Forward Bizpedia』は、株式会社マネーフォワードによる、会計/経理/人事労務のお金にまつわる情報を提供しているオウンドメディアです。
Webサイトに、問い合わせや資料ダウンロードなどのバナーを目立つ位置に複数設置しておくことで、ユーザーからのアクションを狙っているのが伺えました。豊富な種類の役立つ資料を無料でダウンロードができるなど、ユーザーに積極的にアピールすることで、思わずクリックしてしまうようなサイト構成になっています。
バックオフィス担当者や個人事業主向けに、すぐに実践できるような役立つ情報を発信していました。
まとめ
本記事ではBtoBビジネスをしている企業が、これからオウンドメディアを始める際に、どのように始めていくのか、また、運営する際に押さえておくべきポイントについて、解説しました。
実際に、BtoBオウンドメディアを運営している企業の活用事例も紹介しているので、自社のオウンドメディア運営に役立てられてはいかがでしょうか。
「これからオウンドメディアを立ち上げたい」「オウンドメディアをもっと成長させたい」という方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。