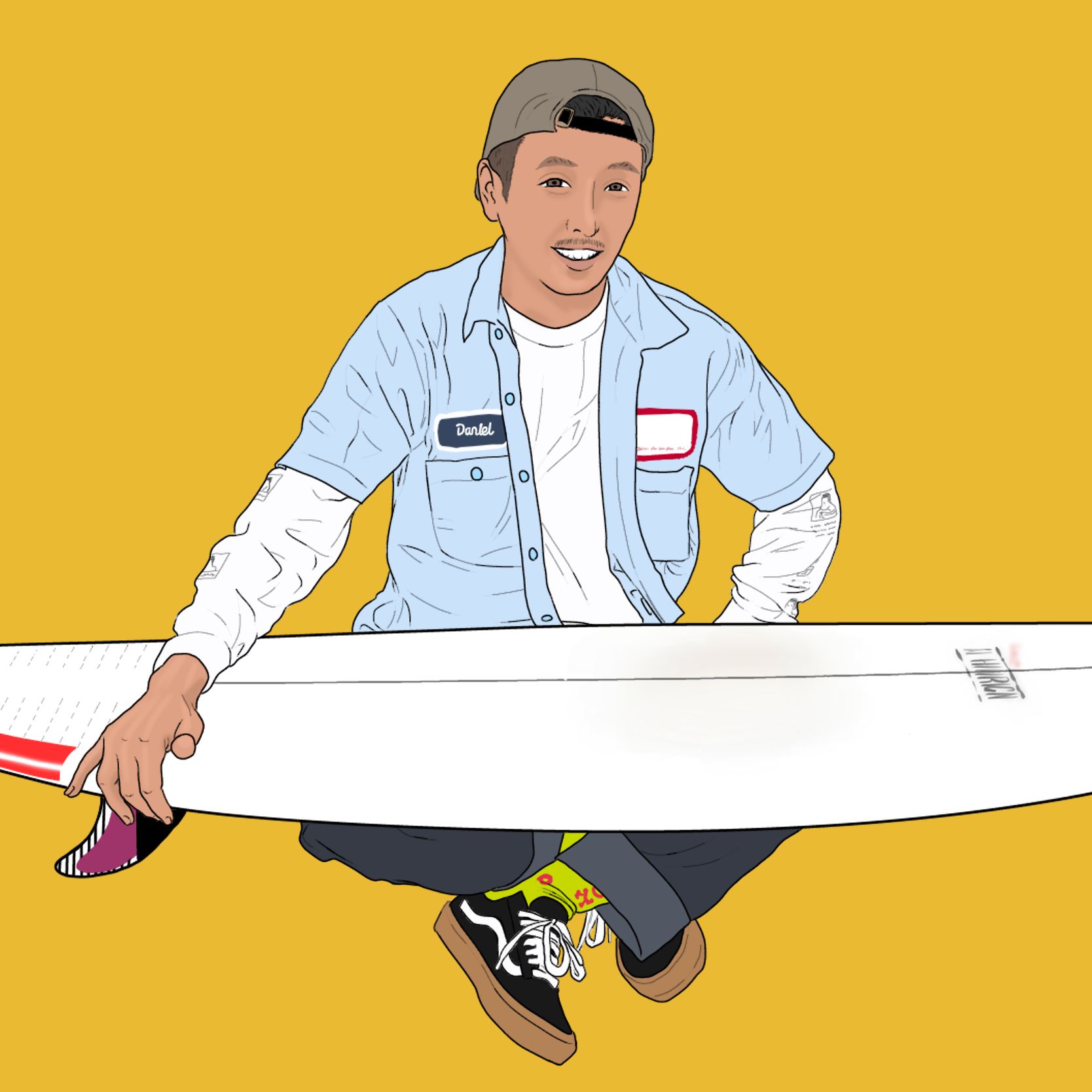昨今、オウンドメディアリクルーティングという言葉を耳にする方も多いかもしれません。聞き慣れない言葉かもしれませんが、企業の採用担当者の間ではよく実施されるものであり、採用活動において重要なことでもあります。
求職者は、企業のさまざまな情報を知るためにあらゆるコンテンツを閲覧するため、採用活動でオウンドメディアを用いることで得られるメリットは多いといえます。
そこで本記事では、企業の採用活動で注目されるオウンドメディアリクルーティングについて詳しく解説していきます。メリット・デメリットに加え、オウンドメディアリクルーティングを実施する流れや求職者が求めているコンテンツなどについても解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
オウンドメディアリクルーティングとは?

オウンドメディアリクルーティングは、「owned media(自分自身のメディア)」を用いて採用活動を行うことを指します。自分自身のメディアというと、個人的なメディアをイメージされる方もいるかもしれません。
しかし企業の場合、オウンドメディアは企業が所有するホームページのコンテンツをはじめ、ブログやSNSアカウントなどを指します。
効率的に企業の魅力を発信するには、多角的な方面で自社の文化・価値観などが発信しやすいオウンドメディアが適しています。近年は、業界を問わずオウンドメディアリクルーティングが採用活動で活用されているケースが増えているのが現状です。
採用サイトとの違いは?
企業が運営する採用サイトは、たしかにオウンドメディアに該当します。しかし、自社が運営するオウンドメディアと比べ、ユーザーに届けられる情報量に違いがあります。
採用サイトによっては求人情報や応募方法などが掲載されているだけの場合もあるため、企業の魅力を発信する場としては不十分です。もちろん、採用サイトに企業の情報を掲載することはできます。社内の雰囲気や具体的な仕事内容などを細かく伝えるのは難しい場合が多いでしょう。
そもそも外部の採用サイトとなると、掲載期間が決まっていたり、掲載できる文字数が決まっていたりするため、期間が満了すれば消失してしまいますし、思うように情報を届けられない可能性があります。
オウンドメディアリクルーティングであれば、求職者に向けて自由に情報を掲載できるため、自社が伝えたい内容を十分に伝えることが可能です。
オウンドメディアリクルーティングが注目されている背景

オウンドメディアリクルーティングが注目されているのには、いくつかの理由があります。ここでは、オウンドメディアリクルーティングが注目されている背景を3つ紹介します。
人材採用そのものの難易度が上がっている
近年は就労人口が減少していることに加えデジタル化の加速などの影響を受け、企業は優秀な人材の確保が困難になってきています。
とくに少子高齢化は深刻で、就職市場において今後は求職者の売り手市場が続く見込みとなっており、これまで通りの採用活動では自社が求める人材を採用できなくなる可能性が高いです。
中でもITエンジニアのように専門性の高い職種に関しては、2022年6月の有効求人倍率が3.6倍と、人材採用そのものの難易度が高くなっています。IT系の職種に限らず、有効求人倍率は年々上昇し続けているのが実態です。
こうした背景から、企業では採用活動の見直しが行われ、採用難の解決策としてオウンドメディアリクルーティングが注目されるようになっています。
求職者の仕事に対する価値観が多様化している
新型コロナウイルスの影響に伴い、多くの企業でリモートワークが普及したのは記憶に新しいでしょう。最近ではライフ・ワークバランスを重要視する人が増え、リモートワークだけでなく時短勤務や副業など、仕事と家庭・育児を両立できる働き方が選ばれるようになっています。
つまり、求職者は自分らしく働ける企業を求めており、仕事そのものに対する価値観が多様化しているのが現状です。
しかし、求人サイトに掲載された情報だけでは、求職者一人ひとりが求める内容を伝えることは難しいといえます。オウンドメディアリクルーティングならば、幅広いニーズに応えるためのコンテンツを自由に発信できるため、求職者が持つ価値観にも対応しやすい特徴があります。
求職者による採用情報等の収集が容易になっている
スマートフォンやタブレットで誰もがいつでも気軽にインターネットにアクセスできる時代になったことで、求職者もまた仕事選びに伴う情報を収集しやすくなっています。
従来であれば、求職者向けの企業のパンフレットや雑誌・テレビなどを参考にしながら情報を入手していましたが、現在はGoogle検索だけでなく、SNSや口コミなどからも有益な情報を入手できるようになっています。
インターネットを活用すれば、膨大な情報の中から自分が知りたい情報だけを探せます。そのため、企業がオウンドメディアリクルーティングを実施して多くの情報を提供すれば、求職者の目に留まる可能性を高めることができます。
オウンドメディアリクルーティングを実施するメリット

企業がオウンドメディアリクルーティングを実施することで得られるメリットは多くあります。ここでは、オウンドメディアリクルーティングを実施するメリットを紹介します。
自社の採用力を高められる
オウンドメディアを採用活動で用いることは、必然的に自社を主体とした活動となるため、採用力を高められるというメリットがあります。
採用活動を行う際には、自社の魅力や求める人材などを明確にして適切な情報を発信していかなければなりません。ターゲットのミスマッチが生じていても、自社管理のオウンドメディアで採用活動をしている場合、方向性など適宜改善しやすいでしょう。
また、オウンドメディアリクルーティングのためのコンテンツを作成し続けていると、人事や経営層の考え方をはじめ、自社の考えを求職者に伝えやすくなります。そのため、自社が求める人材の確保につなげられます。
採用コストを抑えられる可能性が高まる
オウンドメディアリクルーティングを実施していき、高い効果が得られるようになってくると、これまでよりも採用コストを抑えられる可能性が高くなります。
今まで外部の求人サイトで求人情報を掲載していたり、人材紹介サービスを利用していたりした場合は、利用を停止してコスト削減が可能です。
オウンドメディアリクルーティングを実施したからといって、効果はすぐに得られるわけではありませんが、中長期的に取り組み、幅広い情報が蓄積されていくことで結果的に採用コストが抑えられる可能性は高いといえます。採用コスト削減を考えているのであれば、中長期的な視点で続けていくことが必要です。
自社の認知度が向上する
WebサイトやSNSなど、自社のオウンドメディアを開設していくと、それだけ求職者が目にする機会も増やすことができます。オウンドメディアリクルーティングを継続すれば、これまで出会えなかったターゲットに対する認知度も向上させることにつながるでしょう。
とくに、XやInstagramといったSNSで拡散されるようになれば、口コミを通じて自社の認知度が高まっていく可能性もあります。認知度が高まることで、人材採用はもちろん事業全体に良い効果が表れるため、相乗効果が見込めます。
例えば、自社商品やサービスへの問い合わせが増えたり、新たな取引先が見つかったりする可能性があります。オウンドメディアリクルーティングは、求職者の認知度を高め、企業全体に良い影響を与える手法です。
従業員のエンゲージメントが高まる
オウンドメディアリクルーティングは、従業員のエンゲージメント(会社に貢献したい意欲)を高められるといったメリットもあります。
求職者に的確な情報を提供するためには、発信する側である採用側が自社の価値観を深く理解しなければなりません。従業員へのインタビューなどで、経営層の考え方に触れる機会も多くなるはずです。
オウンドメディアリクルーティングを続けていくと、従業員が自社の価値観に共感し、よりやりがいを持って仕事に取り組めるようになります。従業員のエンゲージメントが高まれば、企業の生産性も向上していき、より良い効果が期待できます。
自社の魅力を具体的に伝えられる
一般的な採用サイトや人材紹介サービスを活用する場合、自社の情報を掲載する際に文字数に制限が設けられることになります。掲載ページのレイアウトも決まっており、自社で作成するよりも自由度は低くなってしまう可能性が高いです。
一方で、オウンドメディアは掲載情報の制限もなく、ページのレイアウトも自由に設計できます。イラストや画像を増やして閲覧しやすくしたり、動画を掲載したりすることももちろん可能です。
そのため、自社の魅力や強みもより具体的にわかりやすく発信でき、求職者の共感を得られる可能性も高くなります。情報をより具体的に伝えるには、オウンドメディアは非常に有効な手法です。
潜在層へのアプローチが可能になる
一般的な採用サイトや人材紹介サイトの場合、そこに登録している求職者である顕在層へのアプローチがメインとなります。しかしオウンドメディアリクルーティングでは、Web上で検索してサイトを見つけてくれた潜在層へのアプローチも可能です。
検索して自社のオウンドメディアにアクセスしてくれるということは、今すぐの転職を考えていなくても転職の意識はある程度高い層である可能性があるため、関心を持ってくれる可能性も高いでしょう。転職潜在層へもアプローチできるのは、オウンドメディアリクルーティングならではのメリットといえます。
オウンドメディアリクルーティングのデメリット

メリットの多いオウンドメディアリクルーティングですが、一方でデメリットもあります。オウンドメディアリクルーティングを実施する前に、デメリットについてもよく理解することが大切です。
即効性がなく中長期的な時間が必要となる
オウンドメディアリクルーティングは、実施してすぐに効果が得られるものではなく、中長期的に行って初めて効果が得られるものとなります。そのため、短期的な効果を求めている場合には注意が必要です。
元々自社サイトがなかったり、自社サイトを持っていても採用ページがなかったりする場合は、コンテンツの作成から着手しなければならず、さまざまなコンテンツを充実させるのには時間がかかります。その後、オウンドメディアを用いて求職者からの応募を集めるのもすぐにはできないため、中長期的な視点で取り組むことが前提となります。
初期コストが必要となる
自社サイトがない場合は、オウンドメディアリクルーティングを実施するにあたってサイトを作成しなければなりません。さらに、オウンドメディアのコンテンツを作成するため、企画立案やターゲットを惹きつける画像の設定や文章作成などが必要です。
これまでにこのような経験がない企業であれば、オウンドメディアリクルーティングを導入・運用するための初期費用や体制を整えることに時間がかかります。
また前述したように、オウンドメディアリクルーティングは即効性がなく、中長期的に取り組まなければ効果は発揮されません。コンテンツを充実させて効果を得られるようになるまでは、初期コストが必要になることを念頭に置かなければいけません。
オウンドメディア運用のノウハウが必要となる
オウンドメディアリクルーティングの実施には、サイト運営に関するノウハウが必要です。
従来通りの採用活動とは異なり、採用マーケティングにおける知識も必要になってきます。マーケティングに強い人材が自社にいれば良いですが、そうでなければ採用担当者が自ら専門知識を習得しなければなりません。専任となる人員を確保しなければならない場合もあります。
社員の連携や協力が不可欠となる
コンテンツを充実させるにあたり、担当者は自社の理念・文化・社風など、価値観を深く理解した上で作成しなければなりません。また、従業員のインタビューを掲載する場合も多くなります。
このように、オウンドメディアリクルーティングを継続していくには、従業員の連携や協力が欠かせません。オウンドメディアリクルーティングを実施する前には、自社の従業員に協力が得られるかどうか確認したり、オウンドメディアリクルーティングの重要性を伝えて経営層から働きかけてもらったりして進めていく必要があります。
オウンドメディアリクルーティングを実施する際の流れ

オウンドメディアリクルーティングを始めるためには、いろいろと準備が必要です。ここでは、実施する際の流れをご紹介します。
採用ターゲットを決定する
ターゲットに合わせてコンテンツを作らないと、オウンドメディアリクルーティングの効果が発揮されません。ターゲットによって、コンテンツを発信する媒体が変わる他、オウンドメディアリクルーティングの方向性・カラーも異なります。
そのため、まずは採用ターゲットを明確にすることが大切です。
採用するポジションを確認し、職務と求めるスキルの把握に努めましょう。採用サイト内に職務内容や必要なスキルを明記することで、ターゲットと応募者のズレを防ぐことができます。
実際に採用ターゲットを決めるときは、自社で活躍している人材をベースに考えることがポイントです。活躍している人物が持つ学歴や経験・志向性などを洗い出すことで、自社で求める人材像が明確になります。
自社の特徴/強みを整理する
オウンドメディアリクルーティングを成功させるためには、コンテンツを通じて求職者に自社の魅力を伝える必要があります。
採用ターゲットが惹かれる魅力を考え、その魅力を伝えられるコンテンツを作ることで、ターゲットが自社に興味を持ってくれる可能性が高いです。魅力がない企業に人材が集まることはないので、時間をかけて自社の特徴・強みを洗い出すことからはじめます。
自社の魅力は、企業理念・業務内容・働き方・社員などカテゴリーに分けて考えると見つけやすくなります。社員から最終的に入社を決めた理由や自社の強み・入社後のギャップを聞くのも大切です。社内だけではなく、顧客や取引先といった社外からの客観的な意見も参考にしてみましょう。
自社の特徴・強みを整理する際は、競合他社と差別化できる要素があるかどうかもチェックが必要です。自社の魅力が競合と似ている場合、差別化が難しくなり求職者に魅力を伝えきれない可能性があります。自社のポジションを明らかにして、新しい魅力を発見できないか分析することも大切です。
採用メディアの作成
リクルート用のオウンドメディアがなければ、作成が必要です。オウンドメディアの媒体はさまざまです。
定番は採用サイトです。採用サイトには、募集要項・代表者や社員のコメント・イベント情報・求職者向けコンテンツなど、求職者が興味・関心を持ちやすい情報を抜粋して掲載しています。
社内にWebサイトを作成するノウハウや経験者がいれば、自社でも作成は可能です。しかし、リソースが不足している場合は、オウンドメディアリクルーティングに強いWebサイト制作会社に外注することでスピードを上げた進行が可能です。
この他にも、ブログツールのnoteやWordPress、X(旧Twitter)・InstagramといったSNSなどをオウンドメディアとして活用するケースもあります。どの媒体でコンテンツを発信するかは、採用ターゲットのニーズやオウンドメディアリクルーティングの目的から選ぶことがポイントといえます。
長期的な運用体制を整える
継続的に情報発信していくことで、オウンドメディアリクルーティングの成果につながりやすくなります。したがって、長期的な運用体制を整えることも重要です。オウンドメディアの運用には、主に以下の役割が必要です。
・ディレクター/マーケター:全体的に戦略を練る人
・エンジニア:Webサイトを構築する人
・ライター:記事コンテンツの構成作成や執筆をする人
・編集者:記事コンテンツの校閲や原稿の編集をする人
・フォトグラファー・デザイナー:コンテンツ用の写真撮影やオリジナル画像を作成する人
オウンドメディア全体の戦略を練る人をはじめ、Webサイトのデザインや構築を手掛けるエンジニアや記事を執筆するライターが必要です。コンテンツに誤字脱字や誤った情報がないように、原稿のチェックや校閲・編集を手掛ける編集者も欠かせません。
コンテンツに使う写真・画像は、フリー素材を使う方法があります。しかし、写真・画像にこだわりたい場合はフォトグラファーやデザイナーを設置することが求められます。
これらの役割を自社で用意できない場合、一部またはすべてを外注する必要があります。自社にとってどのような運用体制が継続しやすいのか検討することが大切です。
オウンドメディアリクルーティングで求職者が求めているコンテンツ

オウンドメディアリクルーティングでは、求職者にニーズのあるコンテンツを作り、発信していく必要があります。具体的にどのようなコンテンツが求められるのか、コンテンツ例を見ていきましょう。
社員のインタビュー記事
社員インタビューは、採用サイトでよく取り入れられているコンテンツです。入社のきっかけ・仕事への想いややりがいなど、社員からヒアリングした内容を記事にします。インタビュー記事を通じて、一緒に働く人の顔・価値観などがわかり、どのような仲間と働けるのかイメージしやすくなる点がメリットです。
1対1のインタビューだけではなく、複数人で対談・座談会をして、その内容をコンテンツ化するケースもあります。コンテンツのテーマに合わせて、インタビューのやり方を使い分けることもポイントです。
部署ごとの仕事内容を紹介する記事
企業は複数の部署で構成されており、それぞれ異なる業務を手掛けています。部署ごとに仕事内容を紹介する記事を作れば、求職者は自分が配属された場所でどのような仕事をするのかイメージしやすくなるのでおすすめです。
サムライト株式会社が過去に行った調査によると、新卒・中途のどちらも労働環境や業務のイメージが持てる情報に注目する傾向があることが明らかになっています。
そのため、部署ごとの仕事内容を伝える記事は求職者のニーズの高い情報です。その部署の役割や1日の仕事の流れなどを記事に含めることで、仕事のイメージが湧きやすく、自社に興味を持つきっかけとなる可能性を高められます。
プロダクトやサービスへの想いを紹介する記事
自社が提供する商品・サービスに対する想いを紹介する記事からは、企業の価値観を伝えることが可能です。商品・サービスに対して誇りを持っているということは、仕事への充実感にも関わってきます。
社会に影響を与える仕事がしたいと考える求職者も多いので、そのような求職者に自社の存在意義を強くアピールすることが可能です。とくにプロダクト・サービスの制作に関わる技術職やサービスを広げるための営業職を希望する求職者に響きやすいコンテンツといえます。
開発に携わった社員や責任者にインタビューをして、サービス内容や着想、今後の目標などを語ってもらうこともおすすめです。
経営者の想い・価値観を伝える記事
経営者の想いや価値観を伝える記事も、オウンドメディアリクルーティングでは定番です。経営者にインタビューを行い、創業の経緯やどのような想いを持ちながら経営をしているのか、今後の方針などについて語ってもらった内容を記事にします。
経営者が直接企業や事業に対する想いを語ることで、企業の価値観を強くアピールできます。企業理念や求める人材をメッセージとともに伝えることで、同じ価値観や必要な要素を持つ人材から興味を持ってもらいやすくなるでしょう。
社内のイベントを共有する記事
社内でセミナーや展示会、運動会などさまざまなイベントを開催しているのであれば、その情報を共有する記事もおすすめです。イベントの内容とともに写真や社員のコメントなどを掲載することで、社内の雰囲気を伝えられます。
社内の雰囲気やコミュニケーションの取りやすさなど、組織の文化を重視する求職者も多いです。自分の成長につながるイベントや仕事以外での楽しみなどを伝え、求職者の興味・関心を引くことができます。
社外目線からの自社についての記事
社外の人に自社について語ってもらう記事を作るのもおすすめです。社外の人の意見は、客観的に企業の魅力を伝えられます。また、顧客や取引先などから信頼を得ているという印象を与える効果もあります。
顧客や取引先にインタビューして、自社のプロダクト・サービスを導入したきっかけや導入後の影響など語ってもらい、記事にすることができます。他にも、会社説明会に参加した就活生やインターンシップ生に聞いた感想を記事化して、自社の魅力をアピールする方法もあります。
社内の研修風景や勉強会の紹介記事
企業が実施する研修・勉強会を気にする求職者も多いので、それに関する紹介記事もおすすめのコンテンツです。基本的な研修やキャリアアップにつながる勉強会まで細かく紹介できれば、求職者は教育体制が充実しているかどうか判断しやすくなります。
とくに未経験も歓迎している企業や、研修・勉強会の充実さが自慢の企業は、研修や勉強会を紹介するコンテンツを積極的に発信していくことが良いです。
社内制度や福利厚生に関する記事
研修や勉強会の内容・風景だけではなく、社内制度や福利厚生に関する記事を作成するのも一つの案です。働き方や価値観の多様化によって、社内制度や福利厚生の充実さを重視する人が増えています。
そのため、人材を集めるためには、仕事内容以外にも魅力を感じてもらう必要があります。社員にとって役立つ社内制度・福利厚生があることをメディアから伝えることで、自社に興味を持ってくれる人を増やすことにつながります。
外部の求人媒体では、社内制度や福利厚生が項目内で羅列されているだけということが多いです。そのため、採用サイトなどのオウンドメディアでさらに詳細な内容を紹介することで、働くメリットを伝えられます。実際に制度や福利厚生を利用した社員のインタビューを掲載するのも手段のひとつです。
自社のフォトギャラリー
自社をより深く理解してもらうために、写真や動画を掲載したフォトギャラリーを用意するのもおすすめです。働く社員の姿・表情・職場の雰囲気など、リアルな職場環境がわかる写真・映像を公開することで、求職者に働くイメージを持ってもらえます。
また、プライベートな一面を載せる企業も目にとまります。社員の雰囲気や人柄、社内の人間関係の良さなどを写真・動画から伝えることができます。
オウンドメディアリクルーティングの成功事例5選

オウンドメディアリクルーティングに取り組む企業は多く存在するので、実施する前に参考として企業の成功事例をチェックしてみましょう。ここでは、オウンドメディアリクルーティングに取り組む5社の成功事例をご紹介します。
株式会社ナイル
株式会社ナイルは、インターネットを活用した事業成長支援・自社サービスの開発・運営といった事業を手掛けている会社です。2018年から「NYLE ARROWS(旧ナイルのかいだん)」というオウンドメディアを運営しています。
人・事業・組織・カルチャーのカテゴリーに分けて、組織の取り組みや個人の勤務内容などを発信しているのが特徴です。多種多様な記事がありますが、社員のインタビューが中心となるので、現場のリアルな声も聞けます。
参考:NYLE ARROWS
株式会社ココナラ
株式会社ココナラは、個人の知識や経験、スキルを販売するスキルマーケットを展開する企業として有名です。創業期から採用担当者向けのビジネスSNSの「Wantedly」を活用しています。
Wantedlyのホーム画面では、自社の価値観を明確に表明しています。また、インタビューや対談を中心に、働き方や事業内容、企業理念、メンバー紹介などのコンテンツを発信しているのが特徴です。特定の職種で採用を募集する際は、同じ職種の現職社員のインタビューを紹介し、仕事の魅力を伝えるといった工夫をして、幅広い人材の採用に成功しています。
クックパッド株式会社
クックパッド株式会社は、料理レシピのコミュニティWebサイトの運営を手掛けている会社です。ブログツールのnoteで「クックパッド公式note」を運営しています。
noteでは、広報部のメンバーによるクックパッドの中の様子をはじめ、技術力に関する情報・人事メンバーによる社員や組織、ビジネスの現場に関する情報などさまざまなコンテンツを閲覧できます。食に関わる企業であるため、おすすめの食材やクックパッドに投稿しているおすすめレシピ作者さんの紹介などユニークなコンテンツを展開し、ついつい見たくなってしまう工夫をしているのが特徴です。
参考:クックパッド公式note
フリー株式会社
フリー株式会社は、会計や人事など業務管理を効率化するためのクラウドサービスを展開する企業です。こちらはサービス導入を目的にオウンドメディアを運営していますが、オウンドメディアリクルーティングにも力を入れています。
採用ブログでは、採用に関する全体的な情報を発信しています。記事のカテゴリーが新卒入社・中途採用・freeeについてと分かれているので、目的に合わせて記事を閲覧することが可能です。
また、開発情報ポータルサイト「freee Developers Hub」も運営しています。こちらは開発メンバーが運営しており、仕事の内容や価値観・技術の紹介・イベント情報などを発信し、エンジニアの採用につなげています。
株式会社サイボウズ
株式会社サイボウズは、グループウェアや業務改善を目的にしたソフトウェアを開発している企業です。また、「サイボウズ式」というオウンドメディアを運営しています。
こちらのオウンドメディアは、「サイボウズを知らない人に自社を好きになってもらう」ことをコンセプトに運営されているのが特徴です。会社や組織に関する情報をはじめ、社員の働き方・生き方、家族と仕事の関係性などのカテゴリーでコンテンツを用意しています。
また、社員の単独インタビューや対談だけではなく、他の経営者や専門家など社外の人との対談やインタビューも豊富に掲載し、閲覧者を飽きさせない工夫をしています。
参考:サイボウズ式
オウンドメディアリクルーティングを成功に導くなら伴走型コンサルティングの利用も検討しよう!
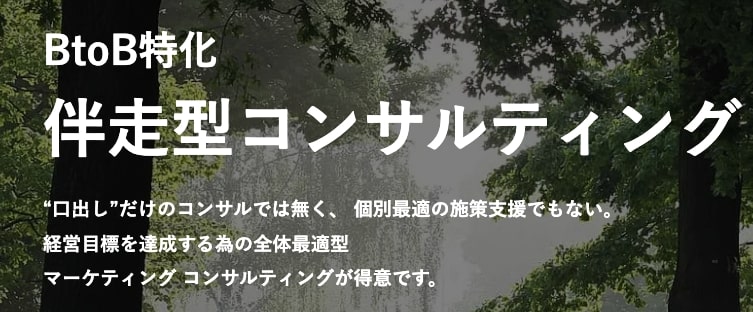
オウンドメディアリクルーティングを実践するにあたって、オウンドメディアを作成・運営するための知識が必要です。コンテンツを作ったら求職者に見てもらう必要があるので、集客も必要になります。オウンドメディアの運営・集客に関する知識が乏しい、社内のリソースが不足しているのであれば、伴走型コンサルティングの利用を検討してみてください。
フォーデザインでは、Webマーケティング領域の各施策のプロを集めた御社専属チームを構成し、マーケティングを支援する伴走型コンサルティングを行っています。記事制作の代行・オウンドメディアや広告の運用代行など課題に合わせて必要なサービスを依頼していただくことも可能です。オウンドメディアリクルーティングのためのオウンドメディア運用や集客などにお悩みであれば、フォーデザインまでお気軽にご相談ください。
まとめ:オウンドメディアリクルーティングを始めてみよう
オウンドメディアリクルーティングには、自社の採用力を高める効果があります。また、メディアで自社の魅力や価値観、仕事内容など、企業の実態・情報を細かく伝えられるので、知名度の向上や求職者とのミスマッチ防止などの効果も期待できます。
オウンドメディアリクルーティングは運営を始めてすぐに効果が出るものではないので、継続的な運営が必要です。
求職者のニーズに合わせたコンテンツ作成や、メディアへの集客も必要となります。リソース不足でオウンドメディアリクルーティングの実現が難しいときは、Webマーケティング領域のプロであるフォーデザインにご相談をお待ちしております。